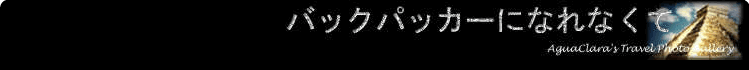
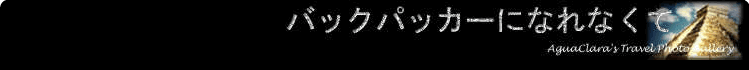 |
|
|
|
ソールズベリ(Salisbury)1999年7月2日 ソールズベリはロンドンから列車で1時間半ほどの街。私が滞在していたホテルはヒースロー空港のそばだったため、空港からバスでまずWoking(ウォーキング)という駅まで行き、そこからソールズベリ方面の列車に乗り込んだ。 ヒースロー空港からはソールズベリ行きのバスも出ていたのだか、2〜3時間に1本と不便だったのと、時間もかかるので鉄道を利用することにした。 ロンドン以外のイギリスの街へ行くのは10年ぶりとあってわくわくする。高校1年の夏に初めてイギリスへ来た頃の新鮮な気持ちがよみがえる。あの頃は草原で羊や牛が草を食んでいる風景を見るだけで「あ、ヨーロッパへ来たんだ。」と感動していたものだ。 ヒースローからソールズベリまでの道のり
ソールズベリ到着後は街へはすぐに出ず、駅からまずはストーンヘンジへと向かった。ソールズベリの街を歩いたのはストーンヘンジから帰りついた午後になった。この頃には曇っていた空も青く輝いて大聖堂の塔に光が反射してまぶしかった。 ソールズベリの見所 ソールズベリ&南ウィルストシャー博物館 ソールズベリの見所は駅からも見える大聖堂。この大聖堂が有名なのは、 イギリス国内で最も高い尖塔をもつと言うこと、 そしてマグナカルタ(大憲章)の4つのオリジナルのうちのひとつが展示されている、ということからである。 建設時期は1220年から1258年にかけて。当時としてはスピード建設である。そのため、建築様式が英国式初期ゴシック様式で統一できたらしい。一般的に当時のヨーロッパの大聖堂は何世代にも渡って建設が続いたため、ロマネスク様式で始まって最後にはゴシック様式で終わる、なんてものが多いのに、たったの38年で完成したこのソールズベリ大聖堂は異色の存在であるといえるかもしれない。 この大聖堂、入場するにはお金を払わなければならない。大人3ポンド。そしてイギリス一高い塔に上るには大聖堂主宰の「尖塔ガイドツアー」に参加しなければならず、これには別に2.50ポンドがかかる。 「観光地へ行ったら高いところへ上ってしまう」という法則につい従ってしまう私は当然のごとくこのツアーに参加することにした。地元で生まれ育ったという75歳くらいのガイドさんについて大聖堂の一角にある木のドアから塔の入り口へと入る。階段を10段ほど上ったところに椅子とヘルメットが並べられた踊り場があり、そこで10分ほどブリーフィングを受ける。この大聖堂の成り立ちや、建築様式などの話しを聞く。ツアー参加者は私のほかにはアメリカ人の親子3人とやはり同じくアメリカ人の軍人さん一人の計5人。 「イギリス一高い塔に登るんでしょう?このガイドさん、大丈夫なのかな?」と若いとは決して言えないガイドさんを見て私は思った。でもこの心配は杞憂に終わる。というのも、このツアーでは塔だけをひたすら螺旋階段に沿って上るのではなく、聖堂の裏や屋根の構造を見学したり、途中の見晴らし台から街を眺めたり、時計台の構造を見たりしながら頂上までたどりつく、というのんびりとしたコースだったからだ。 ガイドさんは聖堂について説明するのが楽しくて仕方がない、といった感じで、細かいところまで説明を加えてくれる。聖堂の天井に沿って緩やかにカーブを描く梁を指差しては「"This shape is so beutuful."ほら、美しいですね、この梁のカーブを見てください。これも13世紀に作られたものなんですよ。」といった具合。 見晴らし台からは「あのレンガの屋敷。あれは映画゛ある晴れた日に"の撮影でつかわれた家ですよ。そしてあの目の前に見える学校は私もかつて学んだグラマースクールで、その頃の校長が有名な作家のXXXX(なんと言う名前なのか忘れてしまった)で、私も彼に教えてもらいました。」なんて教えてくれた。 それにしてもきれいな眺めだなあ。赤い屋根のまちにを囲む緑にエイボン川が流れ、午後の光がまぶしい。 2時間があっという間のツアーだった。ガイドさんの英語もきれいで分かりやすかったし、参加して良かった。 ツアー後、マグナカルタの原本のある回廊沿いのチャプターハウスへ。ところでマグナカルタって何だっけ?世界史で習ったような…、と思いながらガラスケースに入った文字でびっしり埋まった一枚の羊皮紙を眺める。すると係りのおじさんがマグナカルタとは何か、という話しをしてくれた。 なんでもこれは今の民主主義のルーツとも言えるそうで、その基本精神はアメリカ合衆国憲法ほか、いくつかの民主主義の国々の憲法に取り入れられているそうだ。そしてこの羊皮紙、当時としては高価なもの(今のレートで一枚5千円くらい)だったため、こんなに細かい字でびっしり一枚に埋められているそうだ。しかも、ラテン語で、ほとんどの単語が短縮されているそうだ。そういえば私も小学生の頃、ノートのページが足りなくなりそうになると、無理やり小さな文字でしのいだことがあったなあ、と1215年当時のひとの行為と自分の子供の頃の行為を考え合わせてちょっとおかしくなった。 大聖堂で西洋史を学びついでに向いにあるソールズベリ&南ウィルストシャー博物館 へ行く。 こちらの開館は月曜から土曜の10時から5時まで。そして私が入場したのは4時20分ごろ。もう時間があまりないから、ということで本来なら入場料3ポンドのところ、2ポンドにしてくれた。 この博物館には先史時代からのソールズベリ周辺の歴史展示、陶器コレクション、ウェッジウッドコレクションなどのほかにはストーンヘンジについての展示もある。見かけよりかなり展示室の数も規模も大きく、とても40分では見終わらないな、と思い、メインのストーンヘンジの部屋へ急ぐ。そこにはストーンヘンジがどのように作られたか、とか、どのような道具が'使われたか、などの展示があった。 でも40分ではストーンヘンジの展示以外はほとんど見られなかった。今度またここに来るようなことがあったら最低2時間は必要だな、と思った。 10年ぶりのイギリスカントリーサイド紀行。世界遺産のストーンへンジでは新鮮な空気が吸えたし、大聖堂では13世紀の建築構造の細かさをじっくり見学できたし、マグナカルタも見たし、久しぶりにイギリスの羊や牛も見て、高校生のころの新鮮な気持ちがよみがえって、リフレッシュできた。ロンドンはもはや「旅先」とは捉えられなくなった私には新鮮なイギリス「旅」体験だった。
|
|
|
|